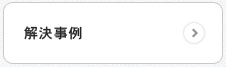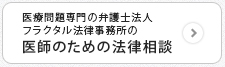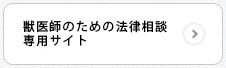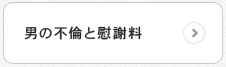著作物を著作権者の許可無く翻案や複製することは、著作権法違反となります。一般的には盗作と言われている行為です。
翻案とは
翻案とは、大まかに言うと、既にある著作物に基づいて、新しい著作物を作る事です。判例上は「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することの出来る別の著作物を創作する行為」と提起されています(平成13年6月28日最高裁判決)。
複製とは
複製とは、大まかに言うと、既にある著作物をそのままコピーする事です。法律上は、「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる著作物を創作する行為」とされています。
このように、翻案、複製ともに難しい定義をされていますが、大まかに、もとからある著作物に乗っかって、新しい著作物を作る(翻案)ことや、そのままコピーすること(複製)は、原則的に著作権者の許可無くしてはならないと考えてください。
盗作かどうかはどのように判断されるのでしょうか。
よくある楽曲と他の楽曲が似ているか似ていないかといった問題で検証するサイトがありますが、ここではあくまで裁判所がどう判断するかというお話をします。
盗作とは何か
盗作とは、法的な用語では、もともとある著作物に①依拠して、②類似している著作物を作成する行為とされています。
ただし、この①、②の要件のうち、①依拠性は、②類似性が認められて、さらにもともとある著作物に接する機会があったことを立証出来れば証明出来るとされているので、①の要件は②が認められれば特別の事情が無い限り認められることが多いです。
そこで、まず②類似性の要件から検討します。
②類似性はどのような場合に認められるか
裁判所はどのような場合に類似していると判断するのでしょうか。
「何となく似ているな」や、「全体としては似てるけど、ここが微妙に違う」といった曖昧な基準で判決を書く訳にもいかないので、どのような基準で翻案や複製に該当するかについて、裁判所なりの基準というのが示されています。
裁判では、この基準に沿って判断されるので、ときどき全体的な印象とは異なる判断が裁判所でされる原因になっています。類似作品を作成する、又は自分が作成しようとする著作物に既に類似の物があることを知った場合、自分や周囲の人の印象だけでなく、裁判所の基準に照らしてどうかという視点も必要でしょう。
濾過テスト
裁判所では一般に濾過テストと言われる方法で類似性を判断することが多いです。
具体的基準としては、①問題となる著作物の間で同一性を有する部分がどこか認定し、②同一性を有する部分が創作性を有するかを検討する(そして、これらの判断要素として、同一性を有する量や、著作物の本質的部分を感得出来るかを考慮する)という方法で行われます
具体的に考えてみましょう。
Aという楽曲がもともと存在しており、このたびBという楽曲が作成されました。AとBとは、似通っている部分があります。Aの作曲者は、自分の作品が盗作されたと考えて裁判所に訴えました。では、AとBとが似ているか否かはどのように判断されるのでしょうか。
まず、裁判所は、①AとBとの似ている部分を切り取ります。楽曲の場合、AとBとの譜面の比較や旋律の比較を行います。
旋律(メロディー)を比較して、似ているところと似ていないところをあげた上で同一性を検討します。旋律の比較方法としては、旋律の印象を基礎付ける音の比較、判例上は、似ている部分をさらにフレーズに分けた上、フレーズの最初の3音以上、末尾、強拍部(拍子の中でアクセントの置かれている拍)が同じかどうか、音が一致している数と全体に対する割合、音の高さの一致率を具体的に検討しています。 次に似ていない部分について、それが旋律の同一部分を覆す程度か創作が加わっただけなのかどうか検討します。 さらに、旋律全体に同一性が認められたとしても、和声(コード)、リズム、形式などの他の要素が旋律の同一性を減殺するレベルのものかも検討して、同一性を判断しています。
そして②同一性を有する部分において、Aという楽曲の創作性を有する部分(一般的なものやアイディアではない部分)がBに表現されているか、それがBから感得出来るかという判断をします。
ただし、以上はあくまでも裁判所で判断される際の基準を大まかに説明したもので、実際は、さらに同一性を有する部分と相違する部分との量や内容の比較、作成の経緯等も考慮しながら総合判断がされることになります。
①依拠性において問題となること
前述したように、②類似性・同一性が認められれば、原則として①依拠性は認められることが多いですが、①依拠性がすんなり認められるかについては問題もあります。
無意識の抗弁
「確かに似ているけど、それは昔に見たり聞いたりしたことがあって、それが無意識に今回の制作の際に出てしまっただけだ」という抗弁です(なお、当サイトでは抗弁という言葉を使用する場合、必ずしもいわゆる要件事実上の抗弁をささない場合もあります)。
このような抗弁は認められ、依拠性が無いとされるのでしょうか。
結論としては、このような抗弁は認められず、依拠性は認められます。
問題点としては「無意識に」の部分、すなわち「依拠していることの認識が無い」ということを理由に、責任が免れるかということです。
前述の例で言うと、他人の著作権を侵害したという場合に必要な制作者の認識は、「Aにわざと依拠してBを制作していること」が必要かということですが、そこまでは必要とされません。依拠性が認められるためには、無意識であったとしても、Aに似たBが制作される際に依拠していたという事実があれば十分となります。
ちょっと難しいですが、無意識であっても、過去に見たり聞いたりしてものが出てしまった場合には、法律上免責されることは無いことになると考えてください。
これは、実質的にも、結果としてBの制作者は、AにフリーライドしてBを制作したわけで、しかもBを制作する認識もあったのですから、やはりAの権利者に我慢をさせてまでBの制作者を保護する必要はないですし、無意識の抗弁を認めると、Bの内心まで立証しないとAは侵害されても保護されないことになってしまい不当ですから、妥当な結論でしょう。
認識可能性の不存在の抗弁
似ている楽曲が既にあったなんて全く知らなかったという場合です。
このような理由で依拠性が無いとされるのでしょうか。
結論としては、この理由は、立証が出来たら認められ、依拠性が無いとされることになります。
なぜなら、偶然の一致の場合には、無意識の場合と違って、無意識にすら依拠していないので、そのような場合には依拠する認識が無いとされるからです。
ただし、類似性が認められることで依拠性が強く推認される関係にあるので、知らなかったという側(被告)は、自分がAという楽曲があることを知らなかった、またはAという作品を知る機会が無かった(例えば海外にいて知らなかったや、究極の場合、逮捕されていたり服役していた等)ことを立証する必要があります。
依拠性の立証責任の問題に引き直せるのか。
上述の無意識の抗弁の話とあわせて考えると、無意識の抗弁の話も、認識可能性の抗弁も、依拠性の立証責任と立証の程度の問題に引き直すことが可能とも考えられます。なお、あくまで以下は私見です。
すなわち、依拠性の立証の程度として、類似性が認められれば依拠性は事実上立証されるので原告としては立証責任を果たした事になる。
よって、被告は、依拠性が無い事の立証をしなければならないが、それは、アクセスの機会が限りなくなかったか、少なくともアクセス機会が限定されていることまで立証しなければならず、単に意識していなかったけど昔にアクセスしてたかも、というレベルでは足りないということです。
このあたりは今後の判例の蓄積が待たれます。
著作料を支払わないカラオケ店舗が存在する場合、歌われた楽曲の著作権侵害者は歌ったお客なのでしょうか。それとも店舗なのでしょうか。
具体例で考えましょう)
JASRACを通じて著作権料を支払うことなくカラオケをお客さんに歌わせているお店があるとします。この場合、歌われた楽曲の著作権を侵害しているとして、カラオケ店舗に対して、著作権者が、損害賠償請求訴訟を行いました。この場合、不特定多数の前で歌っていることを前提とします(実はこの点も問題になるのですが、カラオケボックスでも不特定多数への歌唱にあたるとした裁判例があります(平成9年12月12日大阪地裁判決))。
そこでカラオケ店舗がこう反論しました。
「確かにお客様が歌った楽曲について著作権が存在することは認めるし、誰も著作権料を支払っていないけど、楽曲を勝手に使って歌ったのはお客さんです。うちの店には責任はありません。」
さて、この反論は通るのでしょうか。
前提知識)
著作物を著作者に無断で歌唱することは、著作権者の演奏権を侵害する行為です。ここで大切なのは「歌唱すること」が著作権侵害行為だということです。
カラオケ店舗の反論は原則としてとおりそうな気がしますね。なぜならカラオケ店舗は歌っていないから侵害行為をしていないからです。
しかし、お客さんにカラオケを使わせて利益を得ているのはカラオケ店舗なのに、その店舗に全く金銭を支払わせられないという結論には常識的に考えて違和感があると思います。
さらに、歌っているお客さんから毎回著作権料を徴収することも出来ないので、店舗から著作権料を回収出来ないとなると、実質的に著作権料の回収は出来ないという結論になってしまいます。
そこで、判例法理上、①経営者による歌唱の管理(カラオケの機械の管理)②経営者による営利の追求(営業として行っているということ)を条件に、カラオケ店舗に責任を負担させる理屈を作りました(昭和63年3月15日最高裁判決)。これが「カラオケ法理」と呼ばれています。
このカラオケ法理を応用し、例えば音楽や映画を無許可で違法アップロードしている掲示板の管理者に対しても用いられ(平成15年1月29日東京地裁判決)ています。